先週の台湾訪問中に『周恩来秘録 党機密文書は語る』上下(文春文庫 2010)を読みました。帰国後、新聞広告で目についた『マオキッズ 毛沢東のこどもたちを巡る旅』(カメラマンからフリーランスに転向した八木澤高明著 第19回 小学館ノンフィクション大賞
優秀賞受賞 小学館 2013)を買い求めました。
『周恩来秘録』の著者の高文謙は中国共産党中央文献研究室に長年勤め、天安門事件後、アメリカに渡り膨大な資料と多くのインタービューを重ねて書き上げたもので、第19回アジア・太平洋賞大賞受賞をしています。
文化大革命と中国のその後はなんとなくある程度わかっているつもりでしたが、彼の本を読み、自分の不明を恥じます。これまで周恩来の自伝は読んでそれなりに知っていたつもりでしたが、『周恩来秘録』を読んでみて、中国の現代史に圧倒されました。第19回アジア・太平洋賞の選考委員であった田中明彦氏は、本の最後の解説で、「秘密を知っていれば、第一球の歴史が書けるというものではない。本書の素晴らしさは、単純な善悪二元論によらない、冷徹で立体的な歴史叙述を中国現代史にもたらしたことにある」と記しています。
毛沢東、周恩来、林彪、鄧小平のそれぞれの役割は知っているつもりでしたが、私の知識は表面的なものでした。この本は、毛沢東の性格や心理に焦点をあてながら、周恩来がどのように毛沢東に仕え、それでも嫉妬からか彼を陥れようとする毛沢東に周恩来がどのように対応してきたのか、詳細に記しています。「起き上がり小法師」(不倒翁)とあだ名された周恩来と毛沢東との40年にわたる関係はどのようなものであったのか、そこに林彪や鄧小平はどのような形で関わるのか、大変興味深く読みました。
周恩来の伝記を読み涙したことのある私は、この本で毛に付け込まれないようにする周の違う側面も知ったのですが、それでも彼が自分の地位や立場を守るためにやったというよりは、はやり中国における革命に本気で関わり、病床にあって革命家としての死後の名誉を守ろうとした必死で痛々しい姿を知るようになります。この本ではあまり取り上げられていないのですが、周恩来の死後、政府の禁止令に拘らず何百万人という人たちが彼の死を悼んだという事実からしても毛は彼を貶めることはできなかったということを知ります。あくまでも優しく、驚異的に辛抱強い人でした。はやり惹かれます。
林彪、鄧小平、毛の奥さんであった文革派の江青など歴史上の人物が毛との関係においてどのように振る舞い、どのようになっていったのかその背景をこの本で知ることができました。しかし周恩来の周到でバランスのとれた実務家の姿と対照的なのはこの本の影の主人公である毛沢東です。ともすれば彼の陰湿で嫉妬深い性格から歴史を読み解こうとする
著者の描写から垣間見えるのは、毛沢東の卓越した観察力と指導力・管理能力です。
数千万人が餓死したということから文化大革命を毛の大失敗というのが文化大革命の評価になっていますが、それを毛の嫉妬だとか性格から起こされたものと見ていいのか、私にはよくわかりません。しかしそのような分析は一面的であると感じます。
それにしても文化大革命のあの混乱の中で核実験を進め、大陸間弾道を開発し続け、キシンジャーを迎えてソ連との関係に一定の「落とし前」をつけたのは、私には毛沢東の歴史観があったからではないのか、ましてや、実務家の鄧小平を活用としたのも実は周恩来ではなく、毛沢東だということだと、その眼力には驚くしかありません。
経済発展を願い実務の合理化を徹底する鄧小平と周恩来の目指すことはその通りでしょう。しかし私は社会主義においても資本主義においても国民国家なるものは官僚化し、グローバル化が進み貧困と差別を解消できない人間社会にあって、それを階級問題として捉えその矛盾を解消しようとした毛沢東がどうして今だに世界において影響力があるのか関心があり、『マオキッズ 毛沢東のこどもたちを巡る旅』を読みました。
著者の八木澤は、農村から都市を包囲しゲリラ戦を展開したMaoの思想と実践を見習いアジアにおける影響力を現地を訪ね現地の革命を目指す人と会い、その実態を探ろうとします。ネパールの山村における若い女性革命家の死、中国、フィリピン、理想的共産主義社会をめざし大量の殺人を犯したポル・ポト派のカンボジア、そして私たちの記憶にまだ新しい連合赤軍の陰惨な殺人の現場をそのまさに当事者と訪れます。
バッジやTシャツ、天安門における巨大な肖像画としてのみ存在し、地方格差や階級差別
が露呈されてもはや毛沢東の思想と実践を許さない体制になっている中国の現状を延安や毛沢東の故郷、北京をまわり取材します。
著者はアジアの農村から都市を攻め革命を求めたMaoイズムは全て失敗と見ます。しかしいまだに毛沢東は資本主義とグローバリズムの世界にあって「持つ者と待たざる者」との
格差がある限り、社会の不条理を知った者は「思想や宗教に活路を見い出そうとする。その一つが毛沢東の思想なのだ。毛沢東思想は時代遅れでもなんでもなく、現在進行形で生きていて、この人間社会において資本主義が続く限り、毛沢東は生き続け、巨人であり続けるだろう」と結びます。
著者はこの資本主義社会における「持たざる者」に同情を抱くものの、毛沢東の思想を学ぶことを薦めているのはありません。それに対しては徹底的に批判的です。日本の共産党から連合赤軍に至る「暴力革命」もまた、中国の革命を思想として輸入し、思想を教条化したということを当時の連合責任軍にいた人とのインタビューから明らかにします。殺人現場で自らも愛人を殺害し、最後まで永田洋子と付き合った元連合赤軍のメンバーと殺人の現場を訪れた場面は印象的です。
ネパール、そしてあの悲惨な虐殺を引き起こしたカンボジアにおいても、フィルピンにおいても著者は毛沢東思想に依拠した革命運動は失敗した、それは現実を無視して毛沢東思想なるものを教条化したところにあったとみます。
もちろん著者はグローバル化した資本主義社会の矛盾は直視するものの、それをどう克服するかという処方箋を出すわけでも、問題提起をするのでもありません。フリーのジャーナリストとしてあるがままの情報を伝えるのみです。その行動力から垣間見えた事象はその通りなのでしょうが、私にはノンフィクションライターとしては無駄な、感傷的な記述が多いように感じました。
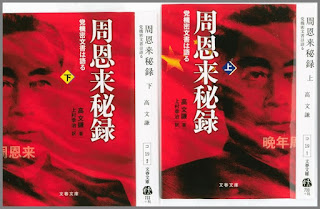





0 件のコメント:
コメントを投稿